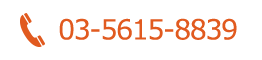〓■〓■〓■〓■〓■ーオフィスエムより皆様へー■〓■〓■〓■〓■
新入社員が入社してから約3ヶ月が経ち、そろそろ職場や業務に慣れてくる頃ではないでしょうか。
しかし、企業にとっては最も注意が必要な時期ともいえます。
というのも、4〜6月は新卒社員による「退職代行」の利用が増加する時期とされているからです。
事前に適切な対策を講じておくことで、退職を未然に防げる可能性もあります。
今回は、退職代行を利用された際にすべきことやトラブルの回避方法を解説します。
入社した社員がなかなか続かない、退職代行を利用されてしまったなど、悩まれている方は、ぜひ最後までご覧ください。
◆退職代行とは
「退職代行モームリ」という名前を、テレビや新聞などで見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。
退職代行とは、従業員本人が企業に直接退職の意思を伝えることなく、第三者が従業員本人の代わりに退職に関する手続きを進めるサービスです。退職代行サービスの運営元は、次の3つがあります。
・民間企業
・労働組合
・法律事務所
運営元によって、サービス内容の範囲が異なります。例えば、従業員がパワハラによって退職する場合、慰謝料の問題が発生する可能性があります。
これは法律的な問題であるため、法律事務所であれば対応できますが、民間企業ではできません。
民間企業が対応できることは、退職の意向や連絡事項を依頼者の代わりに伝えることに限られます。
もし、退職代行から連絡を受けた際は、運営元がどこかを確認する必要があります。
◆退職代行を利用されたことによる企業への影響
退職代行を利用されると、退職者が出るだけでなく、他にもさまざまな影響が出てきます。具体的にどのような影響があるのかを見てみましょう。
・業務に支障が出る
・他の従業員に負担がかかる
・企業のイメージが悪くなる
退職代行を利用されると、企業側は従業員の退職意思を突然知ることになります。
多くの場合、本人はそのまま出社せず、業務の引き継ぎが行われないまま退職に至るケースがほとんどです。
これにより、業務が一時的に停止するなどの支障が出るおそれがあります。
また、残っている従業員が、退職した従業員の業務を負担しなければなりません。
業務量が多くなり、残業時間が増えるなど、他の従業員の負担が重くなるでしょう。
他にも、退職代行を利用された後の対応が不適切だった場合、SNSで悪評が広がり、企業のイメージが下がる可能性もあります。
中小企業では、一人の退職が職場全体に与える影響が大きいため、迅速かつ適切に対応しなければなりません。
◆退職代行を利用されたときに企業が取るべき対応
もし、退職代行を利用された場合、どのような対応を取るべきなのでしょうか。
適切な対応を取れば、不要なトラブルを防止し、組織の健全性を保つことができます。ここからは、企業が取るべき対応を解説します。
1.退職代行の運営元を確認する
まずは、連絡をしてきた退職代行の運営元を確認しましょう。
昨今、民間企業が運営する退職代行サービスが増えていますが、なかには悪質な業者が含まれているケースもあります。
そのため、連絡を受けたら、すぐにやり取りを進めるのではなく、まずは相手の会社名や担当者名などの情報を聞き、実在することを確かめた上で電話をかけなおしましょう。
2.従業員本人からの依頼であるか確認をする
退職代行の運営元が実在する会社であることを確認できたら、次は従業員本人からの依頼なのかを確認しましょう。
めったにないケースですが、第三者によるなりすましの可能性もゼロではありません。
退職代行の運営元は従業員から依頼を受ける際、委任状や契約書の作成、本人確認書類のコピーを取っていることがほとんどです。
これらの書類の提示を求め、従業員本人からの依頼なのかを確認しましょう。なお、確認の際に、従業員本人に連絡をすることは避けましょう。
退職代行を利用している時点で、従業員は企業と直接連絡を取る気持ちはないと考えられるからです。
3.従業員本人の雇用形態を確認する
従業員本人からの依頼であることの確認ができたら、雇用形態を確認しましょう。
従業員の雇用形態によって、企業の取るべき対応が異なるためです。
例えば、無期雇用の場合、民法では退職を申し出てから2週間後に雇用契約が終了すると定められています。このため、企業側が退職を拒否することはできません。
一方、有期雇用の場合、原則として契約期間が終了するまでは退職を認めなくてもよいとされています。
しかし、賃金の未払いやハラスメントの発生、健康への重大な影響などが退職理由の場合は、即日退職を認めなければなりません。
4.退職届の提出を依頼する
退職代行を通じて退職の意思が伝えられた場合でも、退職届の提出を依頼しましょう。
口頭のみのやり取りの場合、のちに「言った言わない」とトラブルに発展する恐れがあるため、確実に書面で残すようにしましょう。退職届が送られてきた場合には、内容に不備がないかを確認します。
5.貸与品の返却を依頼する
もし、企業が従業員にパソコンや制服などを貸与している場合、これらを返却するよう依頼しましょう。貸与品は企業の資産であり、適切に管理しなければなりません。
特にパソコンなど機密情報や個人情報が含まれているものは、情報漏洩リスクを防ぐために慎重な取扱いが必要です。
退職代行を利用している場合、従業員が直接出社して返却することは難しいため、郵送での返却が基本です。
その際、のちのトラブルを防ぐために、返却先や梱包方法、送料負担の有無などは明確にし、伝えるようにしましょう。
6.退職届を受理する
退職届が提出されたら、退職手続きを進めましょう。本人からの連絡でないからといって、拒否することは避けるべきです。
拒否し続けると、法的トラブルへの発展や企業イメージの悪化につながるリスクがあります。退職届が提出されたら、速やかに受理し、適切な手続きを進めることが最善の対応です。
◆退職代行に関するトラブルの回避方法
退職代行を利用された場合、対応を誤るとトラブルに発展するおそれがあります。ここからは、トラブル回避方法を解説します。
◇本人との直接連絡はできるだけ避ける
繰り返しになりますが、本人との直接連絡はできるだけ避けましょう。
退職代行を利用する背景には「会社と直接話したくない」「スムーズに退職したい」などの理由があると考えられます。
このような状況下で、企業が安易に本人へ直接連絡を取ろうとすると、従業員の意向を無視する行為と捉えられ、トラブルを招く可能性があります。
特に、弁護士が退職代行を請け負っている場合、本人への連絡は禁止されます。連絡が必要な場合は、必ず退職代行を通して伝えるようにしましょう。
◇必要に応じて社会保険労務士や弁護士などと連携する
退職代行を利用した際の退職は、通常の退職手続きよりも複雑なケースが多く、法的な知識や専門的な判断を求められることがあります。
例えば、有給休暇の精算や未払い賃金の対応など、細かな労務管理が必要です。
特に、弁護士による退職代行の場合、交渉が発生することもあり、企業側にも専門的な知識が必要です。
こうした場合は、社会保険労務士や弁護士などの専門家と連携を取ることで、適切な対応ができるでしょう。
◇退職手続きを迅速かつ正確に進める
トラブルを回避するために、退職手続きを迅速かつ正確に進めましょう。
手続きが遅れたり、内容に不備があったりすると、依頼者からの不信感を招いたり、トラブルが発生しやすくなります。
◇従業員との信頼関係を築く
退職代行による退職を防ぐためには、従業員との信頼関係を築くことが欠かせません。信頼関係があり、相談しやすい環境が整っていれば、退職そのものを未然に防げる可能性もあります。
例えば、次のような取り組みを行うとよいでしょう。
・定期的な1on1ミーティングの実施
・オープンな意見交換の場の設置
これらを通じて、従業員の悩みや不満を早期に把握し、具体的な改善策を実施していくことで、退職防止につながります。
退職代行による退職の意思を伝えられたら、決して無視せず、適切に対応することがトラブル防止の鍵となります。
突然の退職により、他の従業員の負担が増えることも考えられるため、フォロー体制を整えることも大切です。
退職代行を利用されないためにも、風通しのよい環境作りが求められます。
企業が持続的に成長していくためには、従業員一人ひとりが欠かせない存在です。
今一度、個々の社員と真摯に向き合い、本当に魅力的な企業とは何かを考え、具体的な行動に移していく必要があるでしょう。
参考:
<退職代行とは>
東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反」
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html
ベンナビ労働問題「退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス」
https://roudou-pro.com/columns/262/
<退職代行を利用されたことによる企業への影響>
三重総合社労士事務所「退職代行サービスが増加する中、企業が知っておくべき3つの対応策」
https://www.mh5.jp/announce2_81785.html
HIMOTOKU「【衝撃】退職代行を使われたら?企業が知らないとヤバい対応と注意点」
https://www.himo-toku.com/business/5365/
<退職代行を利用された際に企業が取るべき対応>
MiTERAS「退職代行を使われたら?会社としてとるべき対応を解説」
https://www.persol-pt.co.jp/miteras/column/retirement-agency
HRプロ「「退職代行サービス」とは? 使われた際に企業がすべきことを解説」
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=3924
<退職代行に関するトラブルの回避方法>
d’s JOURNAL「従業員に退職代行を使われたら拒否できない?対処法やトラブル回避の方法」
https://www.dodadsj.com/content/210302_leaving-agency-service/
弁護士法人浅野総合法律事務所「退職代行を使われた会社側の対応は?連絡を無視したらどうなる?」
https://aglaw.jp/taishokudaikou-kaishagawa/#index_id19
みんなの採用部「退職代行対策は?使われたときの対応方法とNG行動」
https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/a-contents-middlecareer-taisyokudaikoutaisaku-250225/
人材アセスメントラボ「なぜ社員は退職代行を使う?理由や企業側がすべき対応、対策などを解説」
https://corp.miidas.jp/assessment/14939/
■〓■〓■〓■〓■なんと新しいシェアハウスはじめました■〓■〓■〓■〓
ステイセーフ西片は「かっこよく生きたい大人女子向けのシェアハウス」です。
女性でも夢をもち、自分で決断をし、自分の足で歩いていく。どんな夢でも叶えるには
自分への投資が必要です。なるべくよい環境でちょっとコストパフォーマンスの高い、
女性のための住環境があればいいなと考えました。
ステイセーフ西片の場所は文京区。昨年リノベしたばかりで、全体的に白く美しい部屋の
シェアハウスが完成しました。文教地区らしく学校や緑が多く、東京大学の近くでとても
静かです。また文京区は安全性も23区で上位に入るエリアで、安心で安全な環境で、
じっくりと自分を見つめることができます。
▼ステイセーフ西片
https://www.officem.jp/%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9/7321/
▼インスタグラムをお使いの方、ぜひフォロー、または「いいね!」をお願いします
【オフィスエム直営女性専用シェアハウス「ステイセーフ西片」】
https://www.instagram.com/stay_safe_nishikata/
女性専用シェアハウス「ステイセーフ西片」の公式動画配信はじめました!
TikTokアカウント @stay_safe_nishikata(WEBからは以下で)
https://www.tiktok.com/@stay_safe_nishikata
※Instagramでも配信しています。
お問い合わせフォーム:https://www.officem.jp/contact/
お問い合わせメールアドレス: mitsumori@officem.jp
■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓■〓
~人手不足解消に「人材のサブスク」してみませんか~
経理でもITでもデザインでも、必要な業務を時期と量に合わせてすぐに依頼でき、採用
にかかる経費も不要。業務に応じて在宅スタッフをチーム編成します。
進行管理のスタッフがお客様とチームをお繋ぎしますので、個別にやりとりいただく必要はありません!
費用は月額3万円からです。
ご相談は、以下のいずれかにてお願いいたします。
お問い合わせフォーム:https://www.officem.jp/contact/
お問い合わせメールアドレス: mitsumori@officem.jp